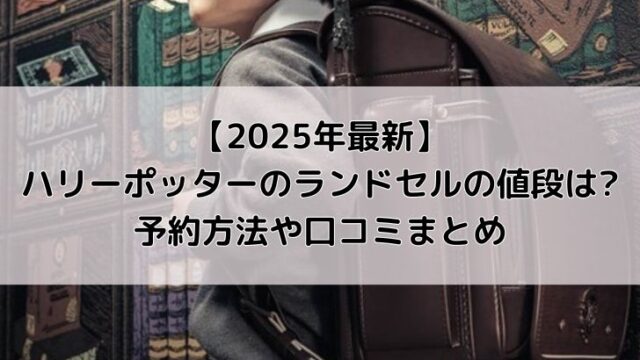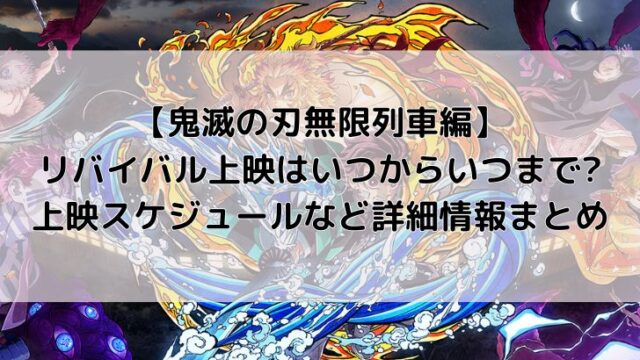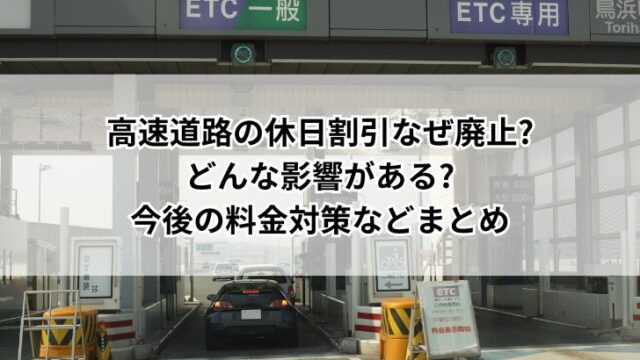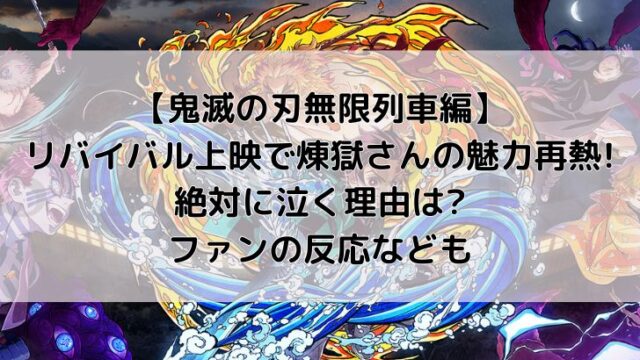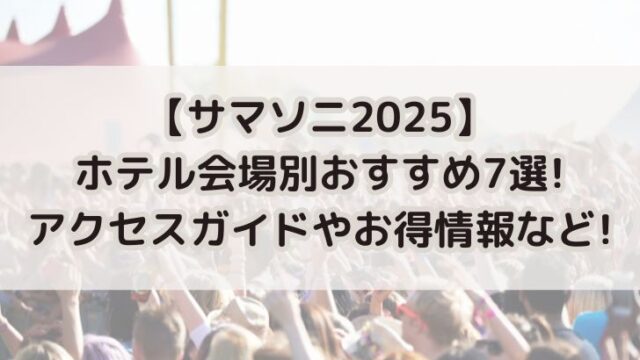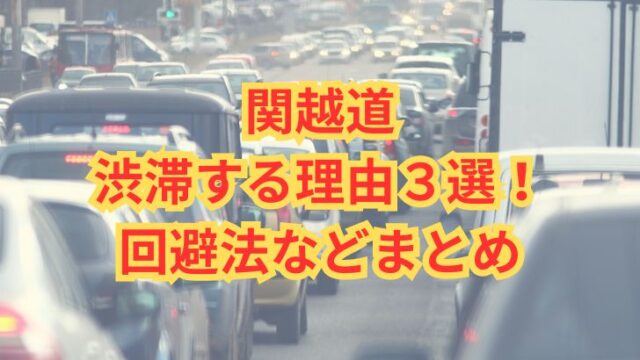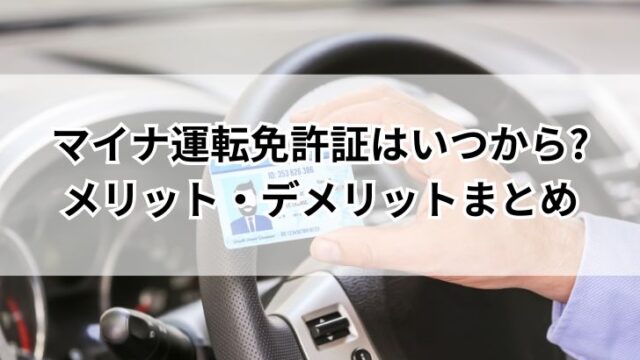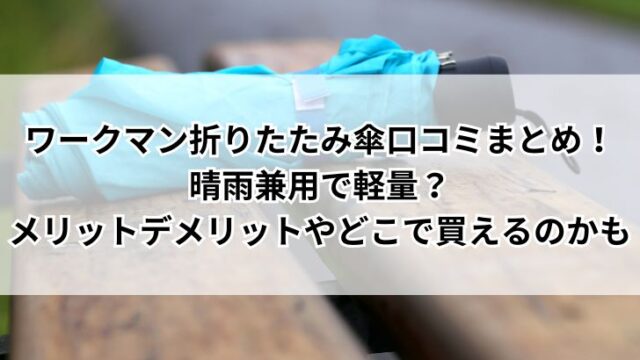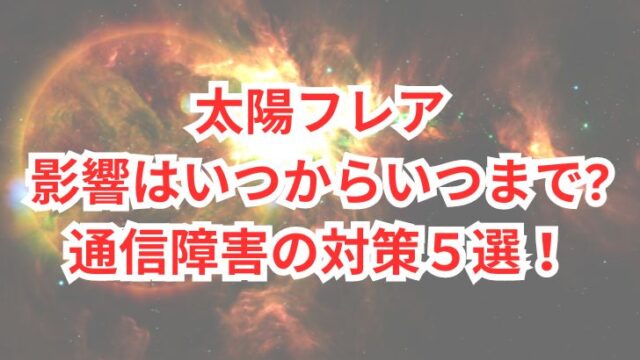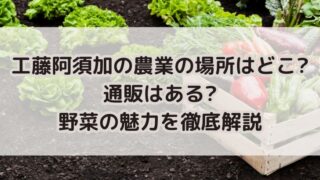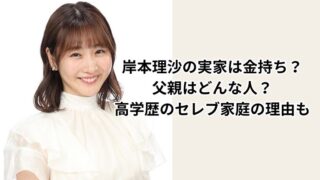2026年から始まる独身税って、いくらかかるの?
最近、「2026年独身税が始まるらしい」「独身の人からもお金を取るって本当?」という話題をよく見かけますよね。
ニュースやSNSでも「独身税いくらになるの?」「なんで独身だけ負担があるの?」といった声が多く、ちょっと不安になった方もいるかもしれません。
でも実は、この「独身税」という言葉は正式なものではなくて、本当の名前は子ども・子育て支援金制度といいます。
2026年4月から始まる予定で、少子化を防ぐためにみんなで子育てを支えるという目的で作られた制度なんです。
そこで、
「2026年独身税って何?」
「いくら支払うことになるの?」
「本当に独身者が損をする制度なのか?」
について、わかりやすくまとめました。
「自分にも関係あるの?」「いくらくらいかかるの?」と気になっている方は、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。
2026年独身税はいくらかかる?
政府の発表によると、2026年の支援金は「ひとり月250円くらい」が目安なんだそうです!
この金額は毎年少しずつ増えていって、2027年には月350円、2028年には月450円になる予定です。
| 年度 | 月額の支援金(目安) | 年間の負担額(目安) |
|---|---|---|
| 2026年 | 約250円 | 約3,000円 |
| 2027年 | 約350円 | 約4,200円 |
| 2028年 | 約450円 | 約5,400円 |
2026年から始まると言われている「独身税」実はこれは正式な制度名ではなく、本当の名前は「子ども・子育て支援金制度」といいます。
この制度は、子育てをしている家庭を社会全体でサポートしていこうという目的で作られました。
そのためのお金をどう集めるかというと、私たちが入っている健康保険の保険料に、ちょっとだけプラスして集める仕組みになっています。
「たった数百円なら、まあ大丈夫かな…」って思うかもしれません。
でも、1年単位で見るとそこそこの金額になるし、何より将来的にもっと増える可能性もあるんです。
制度についてよく知らないままスタートすると、あとで「えっ、こんなに払ってたの!?」って驚くことにもなりかねません。
だからこそ、今のうちからちゃんと知っておくことが大事ですね。
医療保険っていろいろあるけど金額ってどう違うの?
実はこの「独身税(※正式には子ども・子育て支援金制度)」、どの健康保険に入っているかによって支払う金額が少しずつ違ってきます。
同じ年収でも、保険の種類によって負担に差があるって、ちょっと意外ですよね。
会社員(協会けんぽなど)の場合
普通の会社に勤めてる人は「協会けんぽ」に入っていることが多くて、支援金の金額はだいたい平均的。
特別安いわけでも高いわけでもなく、いわゆる標準的なイメージですね。
大手企業の社員(健康保険組合)
大手企業に勤めている人は、会社独自の「健康保険組合」に入ってることが多く、保険の内容が手厚い分、支援金の金額もちょっと高めになるケースもあるようです。
自営業の人(国民健康保険)
自営業やフリーランスの人は「国民健康保険」に加入していて、これがちょっと複雑なんです。
住んでる地域によって支援金の金額が変わることもあるんです。
市区町村ごとにルールが違うので、ちょっと分かりにくいって感じる人も多いかもしれませんね。
しかも、自営業の人は保険料をぜんぶ自分で払わないといけないので、どうしても負担が大きく感じやすいんですよね。
こうして比べてみると、同じ「支援金」でも、どの保険に入ってるかでけっこう金額が変わるんだな〜って感じました。
意外と知らなかった!って人も多いんじゃないでしょうか?
このタイミングで、自分がどの保険に入っていて、どんな仕組みなのかをちょっと見直してみるのもアリですね。
収入が違うとどれくらい負担が変わる?
子ども・子育て支援金(独身税)は、すべての人が同じ金額を払うわけではありません。
保険料が高い人ほど、その中に含まれる支援金の金額も高くなります。
つまり、年収が高い人ほど、支援金の負担も増えるということになります。
これは保険のしくみ上、仕方のないことです。
サラリーマンと自営業、実際どれくらい違うの?
たとえば、年収400万円の人の場合で見てみましょう。
| 働き方 | 月額支援金 | 年間支援金 | 実質負担額 |
|---|---|---|---|
| サラリーマン | 約250円 | 約3,000円 | 約1,500円 (会社と半分ずつ) |
| 自営業 | 約450円 | 約5,400円 | 全額自己負担 |
同じ年収でも、働き方で差が出るから注意
サラリーマンは会社が保険料を半分負担してくれる
自営業の人は全額自分で払うから負担が大きめ
2026年独身税は独身者も対象って本当?
「2026年独身税」という言葉を聞くと、独身の人だけが対象になるように思ってしまいますが、この言葉はあくまで通称(呼び名)です。
本当の制度名は「子ども・子育て支援金制度」といって、少子化を防ぐために、社会全体で子育て家庭を支えることを目的にしています。
実は独身だけじゃない?対象になる人のホントの条件は?
この制度の対象になるのは、独身の人だけではありません。
健康保険に入っている人なら、既婚・未婚に関係なくみんなが対象になります。
つまり、「独身だから払わされる」というわけではないのです。
なぜ独身税と呼ばれてしまうの?
「えっ、なんで私が払うの?」と思っちゃう人も…
正直なところ、「子どもがいない自分にはメリットないのに、なんでお金だけ取られるの?」って感じる人も少なくありません。
こういう気持ちから、いつの間にか「独身税」なんて言葉が出てきたとも言われています。
実際、子育て中の家庭は支援を受けられるけど、子どもがいない人にはその恩恵があまりないことも多い…。
だからこそ、「ちょっと不公平かも?」ってモヤっとしてしまう人もいるんでしょう。
扶養に入っている人・主婦(夫)はどうなる?
たとえば専業主婦(主夫)とか、家族の扶養に入っている人は、保険料を自分で払っていない場合が多いですよね。
そういう人は、支援金も直接は払わなくてOKなんです。
じゃあ誰が払うの?ってなると、
その人の保険料を払っている世帯主さんなどが、まとめて支払うことになります。
だから、「自分は払ってないけど、実は家族がカバーしてる」ってケースもあるんです。
独身だとやっぱり損?制度の公平さってどうなってるの?
「結局、独身の人って損なの?」って思う人も多いのではないでしょうか?
子育て世帯への支援が充実する一方で、子どもがいない人にはあんまりメリットが感じられないってこともありますよね。
でも、この制度はあくまで「みんなで社会を支え合う」という考え方がベースになっているんです。
将来、誰かが子どもを育ててくれたおかげで、社会が回っていく・・・
そんな長い目で見た「支え合いの仕組み」とも言えるかもしれません。
とはいえ、「今の自分」にとって不公平に感じるのは自然なことです。
だからこそ、「本当に公平な制度って何だろう?」って考えるきっかけになるのかもしれませんね。
2026年独身税の1年あたりの負担額は?
さきほども紹介したように、2026年度の平均的な支援金は月250円ほどです。
これを1年分で計算すると、3,000円くらいになります。
そして2027年は年間4,200円、2028年には5,400円ほどになる予定です。
会社員・公務員・自営業で違いはある?
働き方によって、保険料の計算方法が違うため、支援金の金額にも差が出てきます。
| 職種 | 保険制度 | 年間負担額(予想) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 会社員 | 協会けんぽ | 約3,000円 (実質1,500円) | 会社と半分ずつ負担 |
| 公務員 | 共済組合 | 約3,000円 | 組合によって異なる |
| 自営業 | 国保 | 約5,000〜6,000円 | 全額自己負担 |
300万・500万・700万で支援金の負担を比べてみた!
年収が上がると、そのぶん保険料も高くなるので、それにあわせて独身税の金額も変わってきます。
ここでは、ざっくりとした目安として、いくつかの年収ケースで比較してみました。
ケース別の試算(年収ごとに見てみよう!)
| 年収 | 支援金(月額) | 支援金(年間) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 300万円の人 | 約200円 | 約2,400円 | 保険料も控えめなので支援金も少なめ |
| 500万円の人 | 約350円 | 約4,200円 | 平均的な水準の負担感 |
| 700万円の人 | 約500円 | 約6,000円 | 高めの保険料に応じて支援金もUP |
あくまで目安の数字ですが、年収が上がるほど、少しずつ支援金の金額も増えていくのがわかりますね。
将来、支援金(独身税)はもっと増えるの?政府の考えは?
実はこの支援金(独身税)、「最初は少なめに、でも少しずつ増やしていく」っていう方針で進められてるんです。
つまり、今はまだ控えめな金額でも、将来的にはアップする可能性も…ってことなんですね。
特に、少子化の状況がさらに進んだ場合は、支援金の金額もそれに合わせて見直されるかもしれません。
政府としては、長期的な視点で制度を強化していく方向を考えているみたいです。
今からできる家計対策って?
月に数百円といえど、家計への影響はゼロではありません。
支援金(独身税)、今は少ないけどこれから増えるかも…」って聞くと、やっぱりちょっと不安になりますよね。
ここでは、支援金制度に備えてできるちょっとした家計対策をいくつか紹介していきます。
どれも今日から始められるものばかりなので、ぜひ参考にしてみてくださいね!
支援金にそなえる!カンタン家計対策5つ
① 固定費を見直してみる
スマホ代、サブスク、電気代などの毎月自動で出ていくお金をチェック!
格安プランに変えたり、使ってないサービスを解約するだけでも、月500円〜1,000円くらいの節約になることもあります。
② 「支援金専用」の小さな積立を始める
例えば、毎月500円だけ別の口座に積立てておくだけでも違います。
「将来の支援金に使うお金」として用意しておけば、いざ増額になっても焦らず対応できます。
アプリで自動積立できるサービスも便利です。
③ 保険の内容を見直す
医療保険やがん保険など、保険料がかかっているものの内容や金額をチェックしてみましょう。
「重複してる?」「実は不要?」な保険があれば見直しを検討してもいいかもしれません。
家計のムダを減らすことで、支援金分のゆとりもつくれます。
④ 市区町村のサポート制度を確認しておく
自営業の方や国保加入の人は、地域によって保険料の軽減制度があることもあるようです。
意外と知られていないので、役所のホームページや窓口でチェックしてみて下さい。
「実は対象だった!」ってこともあるかも!
⑤ 無理せず、できることからコツコツと!
大事なのは、いきなり完璧を目指さなくてもいいってことです。
「できそうな対策を1つだけでもやってみる」ことが、将来の安心につながります。
まとめ
今回は、「2026年独身税はいくらかかるの?」「独身者だけが対象なの?」といった疑問にこたえる形で、2026年4月から始まる「子ども・子育て支援金制度」についてやさしく解説してきました。
- 「独身税」は正式な名称ではなく、あくまで通称
- 実際の制度名は「子ども・子育て支援金」で、独身だけが対象ではない
- 健康保険に加入しているすべての人が支払い対象になる
- 支援金の額は、2026年は月250円 → 年間3,000円くらいからスタート
- 年収や加入保険、働き方によって負担額が変わる場合がある
- 集められたお金は、子育て支援や少子化対策に使われる
「2026年独身税いくらかかるの?」と不安に感じていた人も、内容を知ることで少し安心できたのではないでしょうか。
今後も制度の詳細は変わる可能性があるので、自分に関係がありそうかどうかをこまめにチェックすることが大切です。
知っているだけでも将来の備えになりますし、少しずつでも準備していくことで安心につながっていくのではと思います。